株取引と損益通算、繰越控除

含み損益になっている銘柄については、損益通算や繰越控除
年末に近づくにつれて、気になるのが所得税や住民税ですね。1年間(1月〜12月まで)の所得に対して課税されるためです。少額投資非課税制度(NISA)を使って株式や株式投信などで運用する場合は税金の心配はありませんが、課税口座の取引では節税対策を考えたいものです。
源泉徴収ありの特定口座で単一の口座
個人投資家の多くは、証券会社の源泉徴収ありの特定口座を使います。株式や投資信託を売却して利益を出したり、配当、分配金を受け取ったりすると、その都度、所得税15%、住民税5%の合計20%の税金がかかります。税金は証券会社が源泉徴収します。
同じ口座で株式などの売却損が出れば、証券会社が他の売却益や配当などの利益と相殺するため、課税対象額が減り、税額も減ります。
つまり、同じ口座の取引は証券会社が年間を通して税金の計算や納税をしてくれるため、自分で手続きをする必要はありません。
源泉徴収ありの特定口座で複数の口座
ただし、源泉徴収ありの特定口座でも複数の口座を保有しており、その中に年間の売却損益がプラスとマイナスの口座が両方あれば、それらの損益を合計する「損益通算」をすれば節税となります。
この手続きは証券会社は対応しませんので、個人が自分で確定申告する必要があります。
例えば、A証券の口座で100万円の売却益があり、B証券の口座で50万円の株式売却損があるとします。A証券では利益に対する20%の所得税(15%)、住民税(5%)が天引きされています。B証券は課税される利益がありませんので税額はゼロで、全体の納税額は20万円となります。
確定申告の際、株式などの売却益は、「申告不要(源泉徴収のまま)」、または確定申告して他の運用益と合計する「申告分離課税」を選択することができます。
損益通算したい場合は、「申告分離課税」を選択します。
申告不要だと利益はA証券の利益100万円に対する税額20万円ですが、申告分離課税を選択すると、課税対象となる株式売却益はA証券とB証券の通算差額であるプラス50万円となります。所得税額はその20%である10万円(所得税75,000円、住民税25,000円)となり、納付済みの20万円との差額10万円が還付されます。
繰越控除
「繰越控除」と呼ばれる仕組みもあります。
株式売却損が多額になるなどで、損益通算しても引き切れない損失が残る場合は、翌年から3年間繰り越せます。
例えば、今年、損益通算後も150万円の損失が残れば、来年、再来年、再々来年の将来3年間の利益と通算できます。損失の繰越をするためには、毎年確定申告する必要がありますから、忘れないように申告をしてください。
| 損益通算しない場合の所得税・住民税 | 損益通算した場合の所得税・住民税 | |
|---|---|---|
| A証券口座の売却益 100万円 | 100万円×20%=20万円 |
100万円-50万円=50万円 |
| B証券口座の売却損 ▲50万円 | ゼロ | 同上 |
| 損益通算後の金額 50万円 | 20万円 | 10万円 |
外貨預金と為替差損益

外貨預金の運用と為替差損益
国内の金融機関に預けた外貨預金で為替差損益が発生した場合も、節税できる場合があります。
為替差益は雑所得として損益通算
外貨預金の収益は利子と、外貨から戻したときの為替差益の2つがあり、それぞれに所得税、住民税がかかります。利子は、支払い時に所得税15%、住民税5%の合計20%が源泉徴収され納税が終わる源泉分離課税です。
一方、為替差益は、「雑所得」として取り扱われます。
給与所得者などで20万円を超える雑所得がある場合は、確定申告をして納税する必要があります。為替差益も申告する必要があります。
為替差益は同じ雑所得にあたる会社員の副業の損失などと損益通算できます。
為替差損が出る場合は、公的年金や企業年金、会社員の副業などと通算できます。例えば、外貨預金の為替差益が50万円あった会社員が副業で20万円の損失を出していたら、課税対象となる雑所得は損益通算後の30万円となります。公的年金の所得が110万円ある人が、為替差損20万円を出したら、損益通算後の所得は90万円にできます。
| 種類 | 収益 | 課税方式 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 上場株式、公募株式、投信 | 売却益 | 申告分離方式または申告不要 | 所得税15%、住民税5% |
| 同上 | 配当金、分配金 | 申告分離方式または総合課税または申告不要 | 申告分離:所得税15%住民税5%申告不要:所得税15%住民税5%総合課税:累進税率 |
| 外貨預金 | 為替差益 | 総合課税 | 累進税率 |
| 同上 | 利子 | 源泉分離課税 | 所得税15%、住民税5% |
〇=通算できる
×=通算できない
| 種類 | 収益 | 上場株式等の売却損 | 外貨預金の為替差損 |
|---|---|---|---|
| 上場株式、公募株式、投信 | 売却益 | 〇 |
× |
| 同上 | 配当金、分配金 | 〇 |
× |
| 外貨預金 | 為替差益 | × |
〇 |
| 同上 | 利子 | × |
× |
配当金、総合課税なら控除も
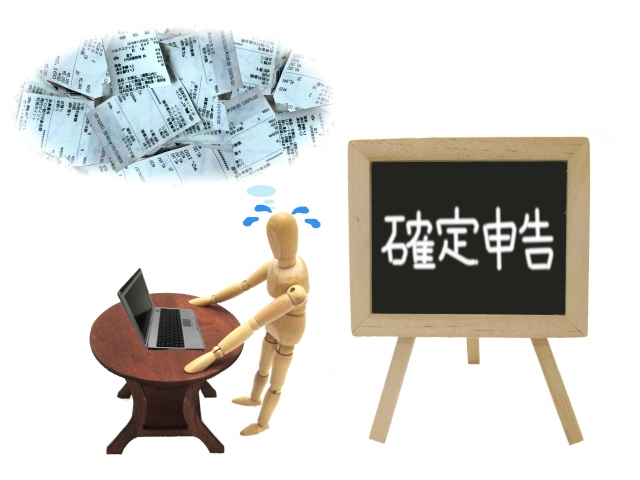
上場株式の配当方式
上場株式の配当の課税方法は、申告不要、申告分離課税方式、総合課税方式があります。損益通算では申告分離を選択します。
損益通算するためには
損益通算するためには申告分離を選択します。
国内株式は、給料など他の所得と合算して税額を決める総合課税を選ぶと、配当にかかる税金の一定割合を軽減する配当控除が適用され、有利になる場合があります。
源泉徴収時の税率は、所得税15%、住民税5%の合計20%。
一方、確定申告して総合課税を選択すると、所得税では所得が多いと税率が上がる累進税率が適用されます。例えば、配当20万円を含めた課税所得800万円だった人が総合課税を選択すると、所得税の税率は23%になります。配当控除率は10%のため、配当にかかる実質税率は13%になります。源泉徴収での税率に比べ低く、節税となります。
ただし、住民税を含めると節税にならないこともあります。住民税率は一律10%です。株式の配当控除率は2.8%ですので実質税率は7.2%です。源泉徴収の税率より高く、節税になりません。所得税を含めた税率も源泉徴収時の税率を超えます。
所得税、住民税の合計実質税率が源泉徴収税率を下回るのは、課税所得695万円以下の場合です。所得税の実質税率が10%以下で、住民税の実質税率7.2%を加えても17.2%以下となり、源泉徴収の税率を下回ります。
一方、課税所得が695万円を超える場合は、「申告不要」が得策といえます。
